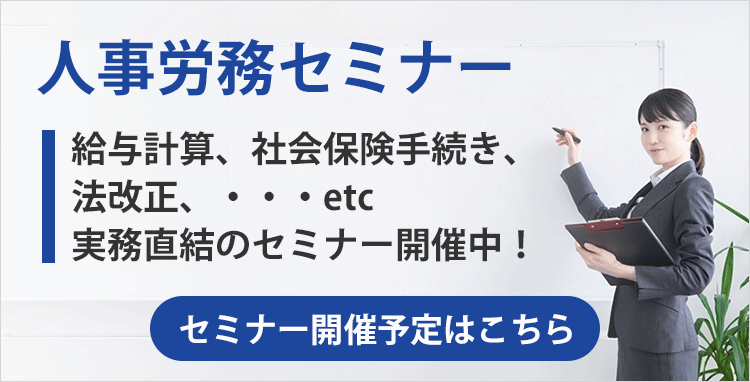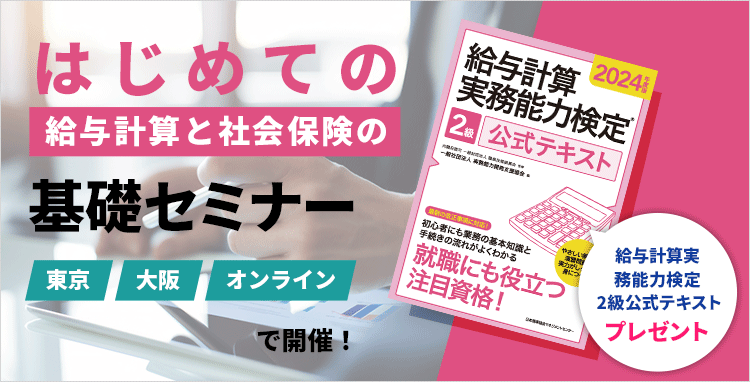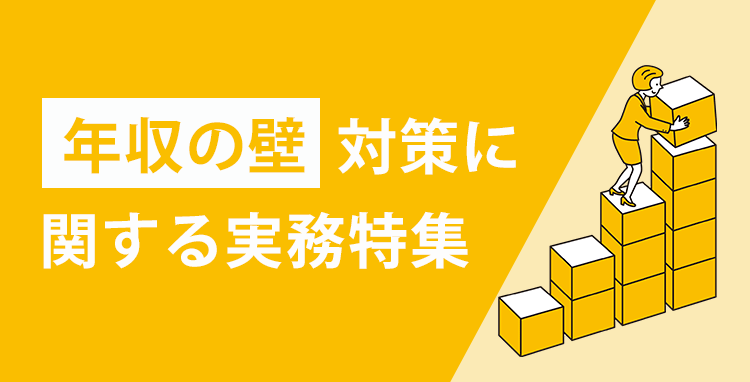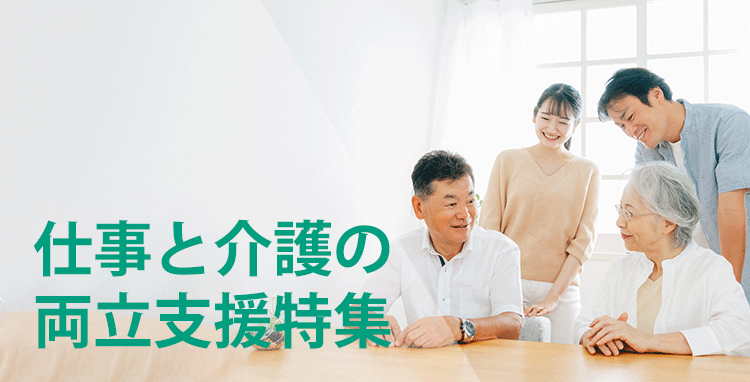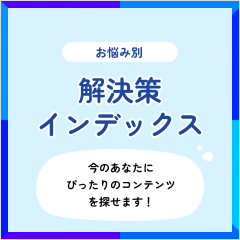部下への懲戒処分等の事案について、監督責任として上司も処分される場合があります。 処分については、就業規則を根拠に行うことになります。程度についても同様ですが、上司が不正を発見できない状態であれば行為者(部下)よりも軽微な処分となるでしょうが、通常の業務の中でちょっと注意をすれば発見できる状態であれば監督不行届きを問うことが出来るでしょう。
ポイントは、部下の行為に対して、上司の監督責任としてどこまで権限が委譲されているかによります。
労働者は法人(会社)と労働契約を締結します。自ら持つ能力・技能等の労働力を、特約でもない限り「自由に使って下さい」として会社にその利用を委ねています。そういった関係の中で代表者(社長)が指揮命令をし、それに従って労務を提供します。しかし、労働者数の増加に伴い、社長一人が全ての労働者に指揮命令をすることには限界があります。そこで、「職制」を設けて権限の一部をその職制の地位にある人に託すわけです。これが権限の委譲です。
つまり、業務上の指揮命令や監督権限は代表者に帰属することを基本とし、例外的に(現実的に)代表者が部長・課長・係長等というような下部職制に権限を配分・委譲して代表者の権限行使させる形です。
従って、職制への任命というのは本来的には権限の授与を意味しています。このことが、権限を委譲された者(上司)が部下に指揮命令をする根拠となり、上司は自分の職制を認識し、部下への指揮監督権限を適正に行使する義務があるのです。部下はその命令に従わなければならない義務があります。
職制の立場としての指導監督義務を怠れば、当然に責任を問うことが出来ます。
例えば、「そのやり方では危険だ。止めなさい。」と常々注意していたにもかかわらず、それを改めずに事故が発生した場合には、上司への処分(社内処分)はゼロではないにしても軽微になると考えられるでしょう。しかし、危険と気づいていながら注意や対策を何も行っていなければ、管理監督者として責任を問うことが出来ます。
同様に、部下が横領したようなケースでは(例えば数千万円)、部下に対する懲戒解雇等の処分は適切と考えられますが、上司への処分は管理監督者としての監督責任の度合いを考慮することになります。 手口が巧妙で通常の注意では容易に気づくことが出来なかった場合は、いくら監督責任があるとはいえ上司を懲戒解雇とするには重過ぎるでしょう。しかし、誰でも容易に見抜けるようであれば監督不行届きを指摘し、多額の損害を発生させたとして当事者と連帯して損害の賠償責任を問うことも出来ると思われます。
このように、各職制における指揮監督権限と、どれだけ誠実にその職制の仕事を行っているかの度合いによって、処分は変わってきます。
日常業務の中で、当然に監督しなければならないことを怠った場合には、職制上の責任が問われることは当たり前のことです。処分を行う際にはその処分の根拠が必要ですので、その職制における職務権限の度合い(仕事と責任の範囲)を就業規則等で明確にしておくことが大切です。
<社会保険労務士 PSR正会員 山下事務所>