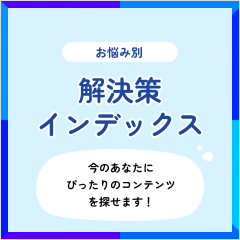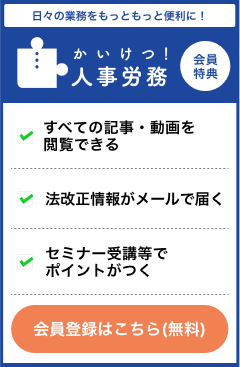福利厚生施策の一環で、企業が従業員に社宅などの住居を提供することがある。従業員のエンゲージメントを高めたいとの考えから、社宅制度の導入に乗り出すケースも少なくないようだ。
ところで、従業員に社宅などを提供した場合、企業や従業員が負担する社会保険料に変化は起こるのだろうか。今回はこの点を整理してみよう。
住まいの提供は「現物給与」の支給に該当
従業員が加入する厚生年金や健康保険、介護保険の保険料額は、給与額に応じた標準報酬月額に基づいて決定される。ただし、この場合の給与額は、必ずしも従業員に支給した現金の額とは限らない。現金以外の方法で従業員に経済的便益を与えた場合にもその便益を金銭換算し、支給した現金と合算して標準報酬月額を判断するのが通常である。
現金以外の方法で提供される便益を現物給与と呼ぶ。典型的な現物給与のひとつが、従業員への住まいの提供だ。従業員に社宅などを提供した場合には、厚生労働大臣が都道府県ごとに定めた「住まいの広さに応じた価額」が原則的な現物給与の金額とされる。
例えば、東京都に所在する企業が都内の賃貸物件を借り上げ、従業員に社宅として提供するとしよう。東京都の場合、現物給与の「住まいの広さに応じた価額」は1畳(1.65㎡)につき月額2,830円である。仮に社宅の広さが8畳だとすると、月額22,640円(=2,830円×8畳)が住宅の提供による現物給与の額とされる。
もしも、現金で支給される給与が月額300,000円であれば、300,000円に22,640円を加算した322,640円を基に標準報酬月額を判断することになる。万一、現金で支給した300,000円のみで判断すると標準報酬月額が本来よりも低く算定され、保険料支払いに不足が生じるので注意が必要である。
従業員の自己負担がある場合は差額が「現物給与」の額に
ただし、従業員が賃料の一部を自己負担する場合には、現物給与の取り扱いも異なってくる。
例えば、前述の東京都に所在する企業が、従業員に月額10,000円の自己負担を求める制度を採用していたとする。このような場合には、原則的な現物給与の額22,640円から従業員の負担額10,000円を差し引いた12,640円が、このケースでの現物給与の額とされる。
従って、現金で支給される給与が月額300,000円であれば、300,000円に12,640円を加算した312,640円を基に標準報酬月額を判断することになるのである。
それでは、従業員の自己負担が原則的な現物給与の額よりも多い場合はどうだろうか。上記のケースで、仮に従業員の自己負担を月額25,000円に設定したとしよう。この場合には、従業員の負担額が原則的な現物給与の額を上回っているので、「現物給与の支給はなかった」とされる。
その結果、他の現物給与の支給がないのであれば、現金で支給される給与額だけで標準報酬月額を判断することになる。そのため、実際の賃料と従業員の自己負担額との差額を企業側が負担したとしても、それによって社会保険料負担が増加することはないのである。
勤務先と社宅の所在する県が異なる場合
現物給与の「住まいの広さに応じた価額」は、下表のように都道府県ごとに定められている。
そのため、隣接する都道府県でも1畳(1.65㎡)当たりの価額が異なるケースが少なくない。それでは、企業と社宅などの所在する都道府県が異なる場合、住宅の提供による現物給与の額はどのように判断すればよいのだろうか。
東京都の企業が埼玉県内の物件を社宅として提供するケースで考えてみよう。現物給与の「住まいの広さに応じた価額」は1畳(1.65㎡)につき東京都が月額2,830円、埼玉県が月額1,810円と大きく異なる。社会保険料負担の軽減を考慮すれば、低い方の金額である埼玉県の月額1,810円を基に現物給与の額を算出したいところだろう。
しかしながら、そのような取り扱いは誤りである。住宅の提供による現物給与の額は、社宅などが所在する都道府県ではなく勤務地が所在する都道府県の価額で計算しなければならないからだ。従って、東京都の額である月額2,830円を基に現物給与の額は算出されることになるのである。

本社と支店が異なる県に所在する場合
次に、本社と支店が異なる県に所在する場合について考えてみよう。前述の「東京都の企業が埼玉県内の物件を社宅として提供するケース」で、同社が埼玉県内に支店を構えていたとする。もしも、埼玉県の支店に勤務する従業員が埼玉県内にある社宅を利用する場合、この従業員に関する現物給与の額はどのように判断すればよいだろうか。
このようなケースでは、埼玉県の支店に勤務する従業員については、現物給与の額は勤務地が所在する埼玉県の価額で計算しなければならない。従って、埼玉県の額である月額1,810円を基に現物給与の額を算出することになるのである。
そのため、同じ埼玉県の社宅を利用する従業員であっても、都内に勤務する者と埼玉県の支店に勤務する者とでは、現物給与の額に相違が発生する。その結果、現金で支給される給与額が同額であっても、「現物給与の相違が原因で標準報酬月額が異なり、社会保険料負担が異なる」という現象も発生し得るのである。
社宅制度を設けている企業では、春の人事異動などで勤務地が変更になった従業員について現物給与の額に変更が生じることがある。その結果、今後、随時改定の要件を満たし、被保険者報酬月額変更届の提出義務が発生するケースも存在する。社会保険事務を担当する皆さんは留意をしていただきたい。
【参考】
日本年金機構:全国現物給与価額一覧表(厚生労働大臣が定める現物給与の価額)
プロフィール
コンサルティングハウス プライオ 代表 大須賀 信敬
(組織人事コンサルタント/中小企業診断士・特定社会保険労務士)
コンサルティングハウス プライオ(http://ch-plyo.net)代表
中小企業の経営支援団体にて各種マネジメント業務に従事した後、組織運営及び人的資源管理のコンサルティングを行う中小企業診断士・社会保険労務士事務所「コンサルティングハウス プライオ」を設立。『気持ちよく働ける活性化された組織づくり』(Create the Activated Organization)に貢献することを事業理念とし、組織人事コンサルタントとして大手企業から小規模企業までさまざまな企業・組織の「ヒトにかかわる経営課題解決」に取り組んでいる。一般社団法人東京都中小企業診断士協会及び千葉県社会保険労務士会会員。
このコラムをお読みの方にオススメの「社会保険」「給与計算」関連コンテンツ
手続きの仕方に迷ったら「社会保険手続きのツボ」

社員の入社・退社、労災が起こった時などケースごとに、帳票の書き方や手続きにおいて気を付けたいことなど基礎からわかりやすく丁寧に解説しています。
手続きの仕方に迷ったらぜひ本ページをチェックしてみてください。
給与計算実務能力検定
 企給与計算実務能力検定試験®は、企業・団体の給与計算業務における知識・実務遂行力の明確な評価尺度として、内閣府認可機関一般財団法人職業技能振興会が給与計算、賞与計算、年末調整、社会保険手続についての法律知識・実務能力を適正に判定し、認定する検定試験です。給与計算未経験の方でも、一般社団法人実務能力開発支援協会が開講する公式試験対策講座、模擬試験講座で学ぶことができます。
企給与計算実務能力検定試験®は、企業・団体の給与計算業務における知識・実務遂行力の明確な評価尺度として、内閣府認可機関一般財団法人職業技能振興会が給与計算、賞与計算、年末調整、社会保険手続についての法律知識・実務能力を適正に判定し、認定する検定試験です。給与計算未経験の方でも、一般社団法人実務能力開発支援協会が開講する公式試験対策講座、模擬試験講座で学ぶことができます。