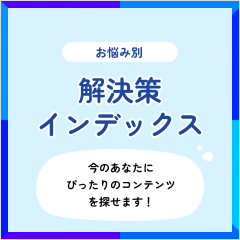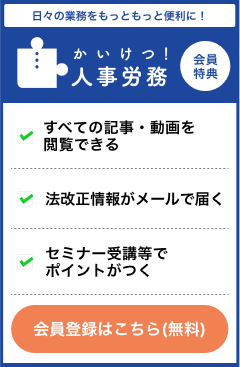危機管理対応における「社内広報」の重要性
<コンサルティングハウス プライオ 大須賀 信敬/PSR会員>
不祥事を起こした企業は「社外への対応」として、メディアを通じて謝罪会見を開くなどの取り組みを行うものである。ところで、不祥事が発生した場合、「社内への対応」はどうすべきなのだろうか。
◆「社外広報」偏重の不祥事対応
企業が不祥事を起こした際、まず問題となるのは「社外への対応」である。たとえば、メディアに対する会見やニュースリリースによる記者発表は、不祥事対応として必ず取り組まなければならない項目である。
また、オフィシャルサイトを通じた謝罪および説明の告知など、顧客に対する情報提供も重要になる。このように、企業では危機管理対応として、「社外広報」による対外的な不祥事対応を行うことになる。
加えて、不祥事が発生したときに重要な項目がもう一つある。「社内への対応」である。つまり、社員に対し、いつ、どのような事情説明を行うのかも、不祥事対応として見落としてはいけない重要事項と言える。このような活動を「社内広報」という。
しかしながら、不祥事が発生した際、「マスコミからインタビューを受けても、何も話さないように」という“箝口(かんこう)令”を社員に対して敷くという対応は行うものの、「今、当社に何が起こっているのか」を社内向けに誠意をもって説明する「社内広報」は、後回しにされるケースが少なくないようである。
◆社内説明の遅れは不信感の増長を招く
仮に、社員に対する事情説明を後回しにしたとしても、社員に対しては外部から不祥事に対するさまざまな情報がもたらされることになる。中には、事実とは異なる不正確な話、悪意ある無責任な情報が混在していることもある。日々、そのような情報にさらされているにもかかわらず、当の会社からは社員に対して責任ある説明が何も行われない、という状況は、極めて深刻である。
自身が勤めている会社が不祥事に手を染めていたという事実だけでも、社員は大いに衝撃を受けるものである。特に、入社から日が浅い若手社員が、そのことを知った驚きと落胆は、想像を絶するものがある。
にもかかわらず、世間の喧騒とは裏腹に会社が社員に何も説明をしないという状況は、社員の不安感・不信感を増長させる以外の何物でもない。このような状況が、会社側にとってメリットになろうはずがない。
ではなぜ、不祥事が発生した場合に、社内に対しては説明が遅くなりがちなのだろうか。もちろん、「社外への対応」に忙殺されるためという側面はあるかも知れない。しかしながら、決してそれだけではないであろう。
例えば、上の立場の者が不祥事に関わっているようなケースでは、「社員に対して事実を話しづらい」、「下の者に対して示しがつかない」などの心理的作用が少なからず働くことになる。それが故に、「まだ、事態の把握ができていない」、「不正確な情報を流すべきでない」などの方便を用いて、社内説明を遅らせる傾向にあるようである。
◆社員もステークホルダーであることを忘れない
企業が不祥事を起こした時には、いかにしてステークホルダー(利害関係者)に対する説明責任を、迅速かつ誠実に果たすかが重要となる。
ただし、この時に決して忘れてはならないことがある。社員もステークホルダーの一員であるという事実である。企業は、社員に対しても大きな社会的責任を負っている。従って、危機管理対応を行う上では、適切な「社外広報」と「社内広報」をきちんと両立させねばならない。
社員に対する迅速かつ誠実な事情説明は、今後の企業再建にとっても必要不可欠な要素だ。危機管理対策を講じるに当たっては、ぜひとも「社内広報」の視点も忘れないようにしたいものである。
プロフィール
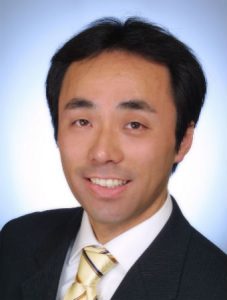
コンサルティングハウス プライオ(http://ch-plyo.net)代表
「ヒトにかかわる法律上・法律外の問題解決」をテーマに、さまざまな組織の「人的資源管理コンサルティング」に携わっています。「年金分野」に強く、年金制度運営団体等で数多くの年金研修を担当しています。