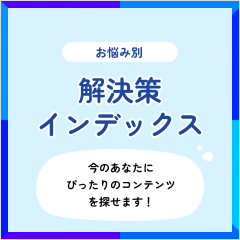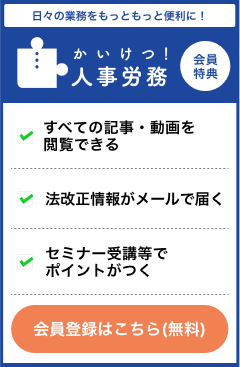【判例に見るパワハラ事例集】
パワハラを防止するため、管理監督者が対応すべき要点とは
<榎本・藤本・安藤総合法律事務所 弁護士・中小企業診断士 佐久間 大輔>
パワーハラスメントの防止に関し、労働施策総合推進法に基づく雇用管理上の措置として、事後対応のほか、主に、パワハラ防止の方針の周知、相談窓口の設置、再発防止研修が挙げられる。
厚生労働大臣による勧告に従わなかったときは公表される。勧告を受けないとしても、体制整備が形式的なものにとどまるのであれば、パワハラは再発するだろうし、使用者責任が免責されることはない。
パワハラ防止には管理監督者の教育が重要となる。本稿では、特に心理的報酬と指示の出し方について述べることとする。
|
関連記事
|
部下に対する心理的報酬
管理監督者は、労働契約上、使用者の安全配慮義務の履行を補助する立場にある。管理監督者は、部下に対し、労働契約に基づき、賃金という経済的な報酬を与えるという本質的義務の履行に関与することはできないが、パワーの源泉となる部下に対して努力をねぎらう、ほめることにより、心理的報酬を与えることができる。
岡山県貨物運送事件・仙台高裁平成26年6月27日判決は、22歳男性の新卒社員(亡一郎)が月100時間超の時間外労働に従事したことにより適応障害を発病して自殺した事案につき、6,941万円の賠償命令を言い渡した。
亡一郎が、疲労のあまり、休憩時間に、休憩室の机の上でうつぶせで寝ていたり、ボーッとしており、反応が鈍かったりするという健康状態の変化が生じたにもかかわらず、上司の営業所長は、自ら配慮をせず、本社の人事労務担当者に相談することもせず、亡一郎に対し、大きなミスがあったときには、「馬鹿野郎」、「そんなことできないのか」、「帰れ」等の激しい言葉を用いて、相当頻回に、他の従業員らのいる前であっても、大声で怒鳴って一方的に叱責することがあった。仙台高裁判決は、亡一郎が自分なりにミスの防止策を検討する等の努力をしたものの、営業所長から努力を認められたり、成長をほめられたりすることがなく、業務により相当強度の肉体的・心理的負荷を負っていたと認定した。
そして、判決は、亡一郎は新卒で採用されたばかりの若年者であり、就労環境や業務の内容にも不慣れであるのに、恒常的な長時間労働を余儀なくされ、その過程で営業所長から頻回に厳しい叱責等を受けていたこと等にかんがみると、亡一郎が抱いていたであろう新たな環境に対する緊張や不安は、自殺に至るまで解消されることはなく、むしろこれらの事情と合わさって、亡一郎の心理的負荷をより強いものとする要因となっていたと認定し、使用者の損害賠償責任を肯定した。
営業所長の叱責は違法なパワハラとまでは認定されていないが、叱責が単独では違法性を帯びなくても、長時間労働や業務負荷が併存すれば、ストレスの相乗作用が起こる。判決は、亡一郎が長時間労働に対してねぎらいの言葉を掛けられることもなく、ただミスに対して営業所長による叱責のみを受け、将来に向けた明るい展望が持てなくなっていったことから自殺に至ったことを認定したが、重い「努力」に対して軽い「報酬」しか与えられないと、これがストレッサーとなる。したがって、部下の努力と報酬が釣り合うようにしなければならない。このようなサポートは管理監督者が自然に身に付けられるわけではないので、人事労務担当者において必要な研修や情報提供を行うことが必要だ。
管理監督者の指示方法
プロフィール
著書は『管理監督者・人事労務担当者・産業医のための労働災害リスクマネジメントの実務』(日本法令)、『過労死時代に求められる信頼構築型の企業経営と健康な働き方』(労働開発研究会)など多数。
DVD「カスタマー・ハラスメントから企業と従業員を守る!~顧客からクレームを受けたときの適切な対応とは~」、「パワハラ発生!そのとき人事担当者はどう対処する?-パワーハラスメントにおけるリスクマネジメント」も好評発売中。
この記事をお読みの方にオススメの「パワハラ」対策コンテンツ
パワハラ発生!そのとき人事担当者はどう対応する?DVD
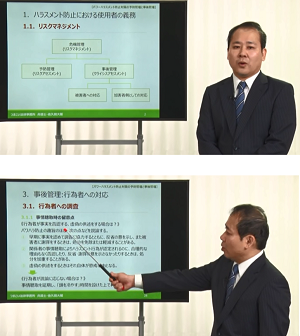 実際にパワハラが発生してまったときにどう対処すればトラブルが避けられるか、また被害が最小限に済ませるには初期対応をどのようにしたらよいのかといった事後対応から、再発防止のために必要な体制整備までを佐久間弁護士が実際に相談を受けた事例や判例を交えて解説したDVDです。
実際にパワハラが発生してまったときにどう対処すればトラブルが避けられるか、また被害が最小限に済ませるには初期対応をどのようにしたらよいのかといった事後対応から、再発防止のために必要な体制整備までを佐久間弁護士が実際に相談を受けた事例や判例を交えて解説したDVDです。ハラスメントの教育・啓蒙に『ストップ!職場のハラスメント』小冊子
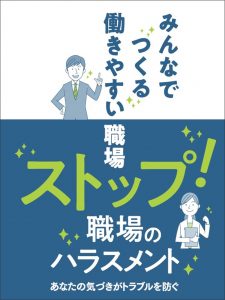 『ストップ!職場のハラスメント』は、2008年の発売からこれまでに累計20万部以上発行している小冊子です。
『ストップ!職場のハラスメント』は、2008年の発売からこれまでに累計20万部以上発行している小冊子です。
ハラスメントを防ぐためには、会社として「しない・させない・許さない」という姿勢を全従業員に周知し、安心して働ける職場環境を整えることが重要です。
この小冊子を活用して、従業員向けにハラスメント防止研修を行うのはもちろん、時間を確保するのが難しい場合、小冊子配布だけでも、会社の方針を従業員に伝え、職場のハラスメント防止意識を高める機会を提供することができます。