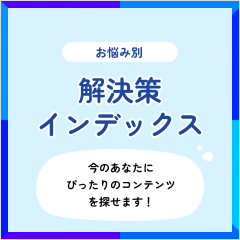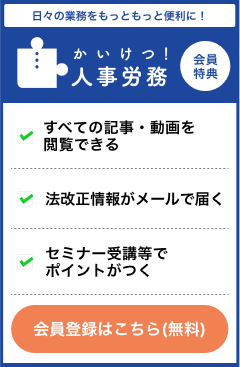この4月に、お子様が小学校、中学校、高校の卒業という人生の節目を迎える方も多いのではないでしょうか。進学や就職という新生活に向けた準備のなかには、税金や社会保険の面でも手続きが必要なものがあります。
扶養は、税金と社会保険の2種類があるためわかりにくく、また、プライベートで忙しく、手続きまで気が回らないことがあります。人事担当者としてそのあたりで社員をフォローできると、後日のお互いの手間も省けます。
この記事では、その節目で必要な手続きを整理しました。
小学校卒業時
小学校卒業時の税金や社会保険に関する手続きは、一般的にはありません。
子が遠方の中学校へ通う等で転居が発生し、社員本人も住民票をうつす場合は、翌年の個人住民税の手続きに影響します。住民票の異動の有無を確認しましょう。
社内規定で、義務教育の始まりである中学入学までは「入学祝金」を出す会社もあるでしょう。扶養に入れていない子も対象としている場合は、人事情報では把握できませんので、プライバシーに配慮しつつ、対象となる子どもの有無を個別に確認しておきましょう。
また、育児短時間勤務制度は、法律上は「3歳に満たない子」までですが、法律を上回って設定している会社もあると思います。小学校卒業までとしている場合は、短時間勤務終了に伴う勤務時間の再確認や、担当業務の見直しも必要となります。
2025年10月施行の改正育児介護休業法では、「小学校就学の始期」に達するまでの子の「柔軟な働き方を実現するための措置」が実施されます。法律では小学校入学後は対象外ですが、子の生活リズムが変わることにより、社員の勤務時間に影響がある可能性もあります。働きやすい環境づくりのため、何か必要なサポートがあるか等の会話ができれば、社員も安心して節目にのぞむことができるのではと思います。
中学校卒業時
プロフィール
和久 明 わく社会保険労務士事務所
小規模な専門書出版社で勤務ののち、社員15万人超の運輸業で社会保険手続き・給与計算・年末調整・業務改善・ライフプランセミナー講師を15年以上にわたり経験。
自身が出版社勤務時代、育児休業制度を知らず取得できていないことから、「知らない人に制度を広めたい!」と社会保険労務士を志す。いつも忙しく手が足りない中小企業の、法改正のキャッチアップ&フォロー、社員の働きやすさ実現、業務の見える化支援に取り組んでいる。東京社会保険労務士会会員。
両立支援コーディネーター、ファイナンシャル・プランナー(AFP)。
このコラムをお読みの方にオススメの「給与計算」セミナー
はじめての給与計算と社会保険の基礎セミナー
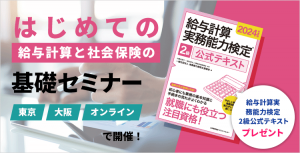 給与計算と社会保険について基礎からの解説と演習を組み合わせることにより、初めての方でもすぐに実務に活用できるスキルが習得できるセミナーです。
給与計算と社会保険について基礎からの解説と演習を組み合わせることにより、初めての方でもすぐに実務に活用できるスキルが習得できるセミナーです。
経験豊富な講師陣が、初心者に分かりやすく給与計算と社会保険の基礎を解説します。
質問がしやすい少人数制。会場受講、オンライン受講、ご自分に合った受講スタイルから日程を選んでいただけます。
>>>詳細はこちら