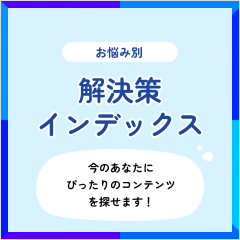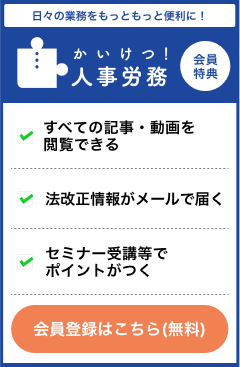介護保険制度の中核を担う「ケアマネジャー」という専門職。
介護保険利用者にとっては馴染みのある専門職ですが、介護保険を利用したことがなければ、普段関わる機会はあまりないかもしれません。
今回は、介護離職防止にもつながる「ケアマネジャー」の役割と、労務担当者として押さえておきたいポイントを解説します。
介護保険の「ケアマネジャー」とは?
ケアマネジャーは、介護保険法第7条の5で定められている「介護支援専門員」のことです。
介護支援専門員の通称がケアマネジャーであり、略して「ケアマネ」とも呼ばれます。
保健・医療・福祉などの分野で相談・援助の業務に一定期間従事した経験者が、資格試験に合格し、所定の研修課程を修了し、登録することで、ケアマネジャーの仕事に就くことができます。
ケアマネジャーの主な仕事は、介護保険利用者やその家族などからの相談に応じて「ケアプラン(介護サービス計画)」を立案することです。
「ケアプラン(介護サービス計画)」は、例えば『定期的に、看護師が訪問する』『週●回、ホームヘルパーが介護・家事を行う』『特殊寝台などの福祉用具を貸与する』など、介護を必要とする等級(要介護度・要支援)に応じた単位数に基づき、ケアマネジャーが立案したものです。
介護サービスを必要とする方が、自立した日常生活を送ることができるように支援することが「ケアマネジャー」の大切な役割といえます。
対象従業員が「ケアマネジャーとの打ち合わせ」に、『介護休暇』の取得を勧める
介護休業制度の中には、年5日まで(対象家族が2人以上の場合は、年10日まで)利用できる『介護休暇』があります。まずは、労務担当者として従業員へ『介護休暇』の周知を行いましょう。
そして、子どもが病気になった時などに「子の看護休暇」を利用することと同じように、急に介護が必要となった時に『介護休暇』を取得するのも一つの方法です。
しかし、それだけではなく「ケアマネジャーとの打ち合わせ」にも『介護休暇』が取得できることを、ぜひ周知しましょう。
1人のケアマネジャーは、一般的に30件を超えるケースを持っていますので、それぞれの対象家族と頻繁に打ち合わせができるわけではありません。
ケアマネジャーとの打ち合わせは、対象家族の日々の状況、今後の介護サービスの方向性などを共有するための大切な場面となります。
対象従業員の「ケアプラン」へ必要な配慮を行う
ケアマネジャーは、対象者と契約してサービスが提供されますので、労務担当者が直接ケアマネジャーと関わることはあまりないかもしれません。
そのため、ケアマネジャーが作成する「ケアプラン」についても、労務担当者が触れる機会もあまりないかもしれませんが、対象従業員の「ケアプラン」の概要を知っておくことは、従業員の‘’仕事と介護の両立支援‘’を図る上で一つの有効な方法といえます。
もちろんその「ケアプラン」の情報を労務担当者と共有するかは、対象従業員が判断するものですので、無理して聞き出すものではありません。
ただ、労務担当者が「対象家族の症状が変化し、定期的に訪問看護が入るようになった」「毎週●曜日に、ホームヘルパーが入っている(それ以外の曜日は、ホームヘルパーが入っていない)」などの情報を知っておくと、従業員への必要な配慮を想定できることへとつながります。
そして必要な配慮を行うためには、介護休業制度などの情報を伝えるだけでなく、日頃から従業員及び対象家族の状況を気に掛ける姿勢も大切となります。
「ケアマネジャー」の仕事と介護の両立支援に関する取り組み
普段は、労務担当者と直接関わることがあまりないケアマネジャーですが、ケアマネジャーを活用した取り組みを推進している企業もあります。
経済産業省「仕事と介護の両立支援に関する経営者向けガイドライン」では、次のような取組例を紹介しています。
|
・東京海上日動火災保険株式会社では、家族の介護に直面している社員の相談を受けるため、両立支援を行う「産業ケアマネジャー(グループ会社に所属)」の相談窓口を独自に設けている。
・ 大成建設株式会社では、社員が利用できる両立支援制度のほか社員本人の働き方やこどもの数・年齢、介護できる時間や希望を含む介護に対する考え方等の記載欄を設けたケアマネジャーへの提出用のリーフレット(仕事と介護の両立相談シート)を作成。 社員が実際に家族介護を必要とするようになった場合に、ケアプランを作成するケアマネジャーに的確に相談できるようにしている。
※経済産業省「仕事と介護の両立支援に関する経営者向けガイドライン」より |
また、厚生労働省ホームページでは「ケアマネジャー研修 仕事と介護の両立支援カリキュラム(令和5年3月作成)」が公開されています。
この資料自体は、ケアマネジャーが、仕事と介護の両立支援について学ぶための研修資料ですが、労務担当者としても活用できるものとなっていますので、ぜひご参考ください。
ケアマネジャーを生かして会社独自の取り組みを実施することは、介護離職を防止するための先駆的なものとなりますが、まずは「介護休暇の取得推進」など、身近にできるところから進めていきましょう。
プロフィール
昭和51年生まれ。日本社会事業大学専門職大学院福祉マネジメント研究科卒業。約20年にわたり社会福祉に関わる相談援助などの業務に携わるとともに、福祉専門職への研修・組織内OFF-JTの研修企画などを通じた人材育成業務を数多く経験してきた。特定社会保険労務士として、人事労務に関する中小企業へのコンサルタントだけでなく、研修講師・執筆など幅広い活動を通じて、“誰もが働きやすい職場環境”を広げるための事業を展開している。
このコラムをお読みの方にオススメの「仕事と介護の両立支援」コンテンツ
『働くあなたを守る 仕事と介護 両立サポートBOOK』小冊子で介護個別義務&40歳の情報提供義務クリア!
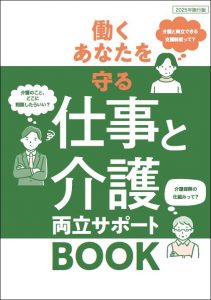 法律で求められることとなった介護に関する周知事項を網羅するとともに、個々人が最適な仕事と介護の両立体制をつくる上で必要な一通りの知識をまとめたのが本冊子です。
法律で求められることとなった介護に関する周知事項を網羅するとともに、個々人が最適な仕事と介護の両立体制をつくる上で必要な一通りの知識をまとめたのが本冊子です。
ぜひ、本冊子を介護制度の周知義務化対応としてだけでなく、介護離職防止策や介護両立支援策の一環としてご活用ください。
>>>詳細・ご購入はこちら
介護従業員説明用セット~個別周知・意向確認、早期情報提供~ NEW!
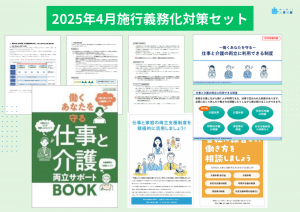 5月末まで1万円割引のリリースキャンペーン中!「介護に関する個別周知・意向確認」「早期情報提供」のすべてが1つで完結!「介護従業員説明用セット」 は、2025年4月から、改正育児介護休業法で義務化されている「介護に関する個別周知・意向確認」「早期情報提供」 の実務対応に特化したセットです。
5月末まで1万円割引のリリースキャンペーン中!「介護に関する個別周知・意向確認」「早期情報提供」のすべてが1つで完結!「介護従業員説明用セット」 は、2025年4月から、改正育児介護休業法で義務化されている「介護に関する個別周知・意向確認」「早期情報提供」 の実務対応に特化したセットです。
>>>詳細・お申し込みはこちら